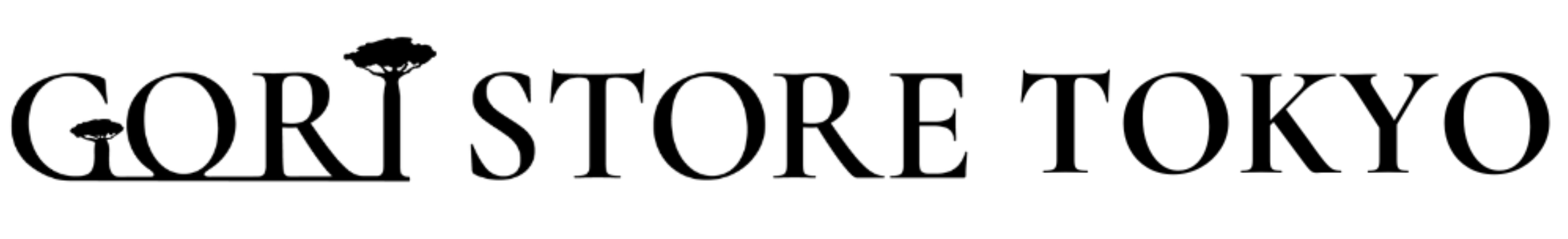GORI日記



首相はなぜ今、衆院解散なのか。何を国民に問うのかが見えない不安
通常国会冒頭での衆院解散案が浮上する中、首相は何を国民に問おうとしているのか。 政策停滞への不安とともに、生活者・経営者の視点から感じた疑問を綴ります。
首相はなぜ今、衆院解散なのか。何を国民に問うのかが見えない不安
通常国会冒頭での衆院解散案が浮上する中、首相は何を国民に問おうとしているのか。 政策停滞への不安とともに、生活者・経営者の視点から感じた疑問を綴ります。

ソフトバンクが進めるAI基地局とは?自動運転とロボット普及を支える次世代通信網
ソフトバンクが2026年から整備するAI搭載基地局とは? エッジAIによる高速通信が自動運転やロボット普及をどう変えるのか、わかりやすく解説します。
ソフトバンクが進めるAI基地局とは?自動運転とロボット普及を支える次世代通信網
ソフトバンクが2026年から整備するAI搭載基地局とは? エッジAIによる高速通信が自動運転やロボット普及をどう変えるのか、わかりやすく解説します。


こだわり続ける性格と、REIGNING CHAMP閉店について思うこと
こだわりが強い性格の私が長年愛用してきたREIGNING CHAMP。その千駄ヶ谷店閉店を知り、服との向き合い方や日常について改めて感じたことを綴ります。
こだわり続ける性格と、REIGNING CHAMP閉店について思うこと
こだわりが強い性格の私が長年愛用してきたREIGNING CHAMP。その千駄ヶ谷店閉店を知り、服との向き合い方や日常について改めて感じたことを綴ります。