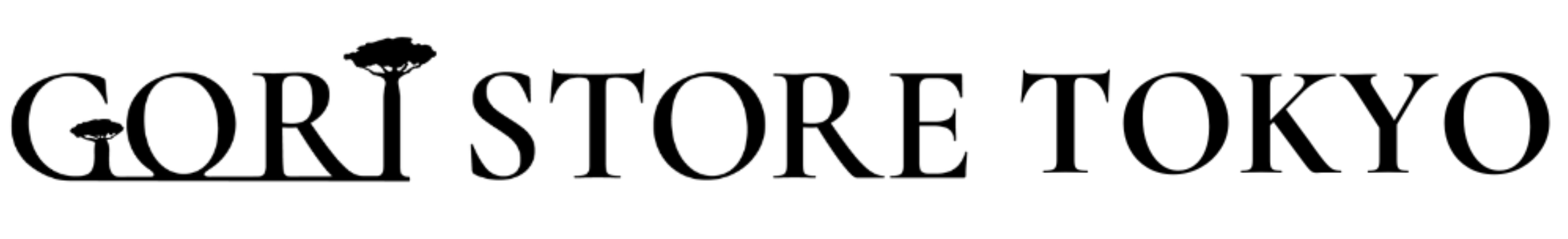こんにちは、GORIです。
最近、新聞で「ギャツビー曲線(The Great Gatsby Curve)」というグラフに出会いました。これは、アメリカンドリームの象徴ともいえる**F・スコット・フィッツジェラルドの小説『グレート・ギャツビー』**にちなんだ経済学的な概念。かつては「努力すれば親以上の人生が実現できる」と信じられていた時代。ですが、今や「子が親を超えるのは難しい世界」が現実になりつつあります。
■ ギャツビーの悲劇と、私たちの現実
1920年代、狂騒のアメリカでギャツビーは貧困から富豪へと成り上がり、過去の恋を追い求めます。しかしその夢は報われず、最後は悲劇を迎える——。100年後の今、彼の物語は単なるフィクションではなく、格差が固定化された社会の縮図として現実に重なります。
米国では上位1%の富裕層が所得や資産の多くを占め、しかもそれが**「相続」「コネ」「独占」**で継承される時代。スタートラインが違いすぎる。どれだけ努力しても追いつけない現実に、多くの若者が夢を見られなくなっています。
■ 親を超えられるか?日本も他人事ではない
「ギャツビー曲線」は、所得格差と世代間格差(親の所得が子にどれほど影響するか)の相関を示すもの。アメリカやメキシコは右上(=格差が大きく、その格差が子どもにも連鎖しやすい)に位置し、北欧諸国は左下(=格差も少なく、子どもが親を超えるチャンスも高い)。
驚いたのは、日本もこのグラフの中間に位置していることです。かつては「子どもの9割が親より豊かになれる」時代だった日本でも、今や半数以下。2人に1人しか親の所得を超えられないという現実。私たちの国でも、「努力すれば報われる」という信念が揺らいでいます。
■ 教育が未来を変える鍵
では、どうしたらこの閉塞感を打破できるのか。慶應大学の赤林教授は「公教育の質」を鍵に挙げています。単に予算を増やすのではなく、**個別最適化された学び(飛び級やデジタル教材の活用)**によって、子どもたちに多様な成長の道を示すこと。制度の柔軟性と本気の投資が求められています。
高校無償化といった"やってる感"ではなく、本気で「親を超えられる教育」を用意すること。それが、100年後のギャツビーを生まないための最初の一歩だと感じます。
GORI