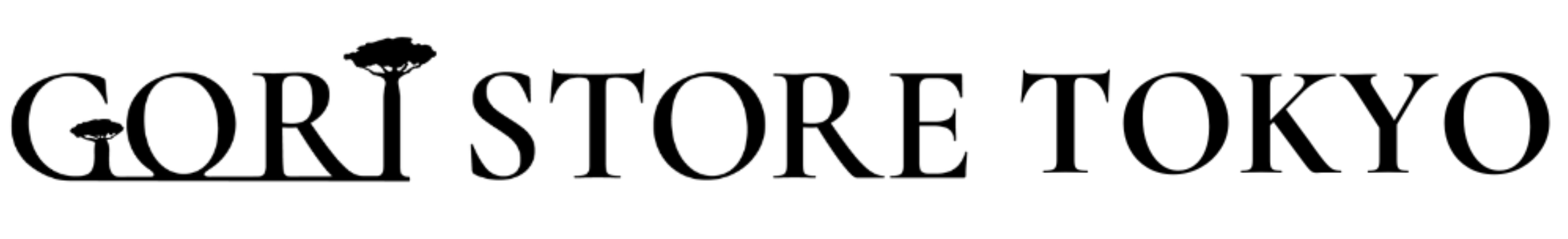こんにちは、GORIです。
最近のニュースで「減る森林、人類を試す」という言葉を目にしました。
世界の森林は伐採や火災で減少を続けながらも、光合成が活発になったことでCO₂の吸収量は増えています。しかし化石燃料の消費による排出が圧倒的に速く、温暖化の進行は止まりません。
森林の現実と日本の課題
森林は地球にとっての大きな肺のような存在ですが、世界銀行の統計では1992年に陸域の33%だった森林は2022年には31%へと減少。
日本では面積は変わらなくても、木の高齢化によってCO₂吸収量が2003年のピーク時から半減しています。
森を守り、伐採と植林をバランスよく繰り返して「若返らせる」ことが急務です。
生き残る力とは何か
ここでふと思うのが、なぜ小さな蟻が生き残れてきたのかということです。
恐竜のように巨大で強力な生き物が絶滅していった一方で、蟻や昆虫の多くは今も地球上で繁栄しています。
その理由は「環境への適応力」にあります。
蟻は群れで協力し合い、食料や住処を柔軟に変えながら生き延びてきました。サイズの小ささも、環境変化に対するしなやかさを生み出しました。
つまり「強いもの」ではなく「環境に合わせて変われるもの」が生き残ってきたのです。
live with plants ― 植物と共に生きるために
私は「live with plants=植物と共に生きる」というテーマを大切にしています。
しかし、気候変動や異常気象の中で、植物もまた試されているのだと思います。
人間も蟻のように、変化に対応する柔軟さを持たなければならない。
森を守り、木を若返らせ、植物と共に歩む知恵を持つことができるかどうか。
それが、これからの時代を生き残れるかどうかの分かれ道になるのではないでしょうか。
今日のまとめ
-
森林は減少し、CO₂吸収の役割が揺らいでいる
-
日本の森は高齢化が進み、若返りが必要
-
蟻が生き残ったのは「環境への適応力」
-
人間も植物と共に、変化に柔軟に対応する力が問われている
「減る森林が人類を試す」という言葉の背景には、実は“生き残るための進化”という普遍的なテーマが隠れているのかもしれません。
GORI