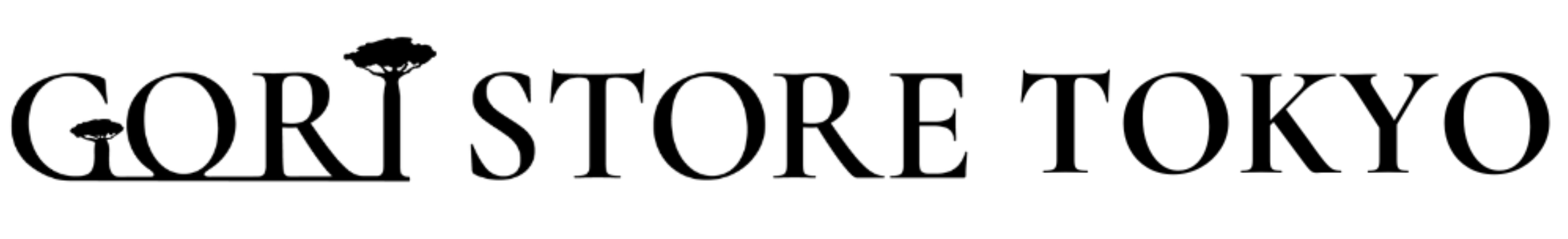こんにちは、GORIです。
最近、ラジオやテレビ、新聞で地震の話題を目にすることが増えた気がします。
なんでかな?と思ったら、もうすぐ3月11日。東日本大震災からまた一つの節目を迎えるんですね。忘れないようにしよう、風化させないようにしようと思っていても、時間が経つのは本当に早いものです。
そんな中、最近「コミュニティFM」が全国で増えているという話を耳にしました。地域に密着した情報を届けるラジオ局で、全国に345局もあるんだとか。特に災害時には、停電でスマホが使えなくなった時にも情報を得られる貴重な存在です。
例えば、北海道函館市の「FMいるか」。
1992年に日本初のコミュニティFM局としてスタートし、地域に根付いた放送を続けているそうです。
きっかけは2004年の台風18号。暴風による停電が続く中、4日間にわたり緊急放送を行ったことで、地域の人たちにとって頼れる存在になりました。
2018年の北海道胆振東部地震の時も、給油可能なガソリンスタンドの情報などをリアルタイムで伝えていたそうです。
宮城県気仙沼市の「ラヂオ気仙沼」も、東日本大震災の後に臨時災害放送局として誕生。
最初は避難所や炊き出しの情報を伝えていたけれど、今では地元の商工業者の情報発信も手掛けるようになり、広告収入も増えて、市の支援に頼らず運営できるほどに成長しているそうです。
でも、全国のコミュニティFMの4割以上は赤字経営。
新しく開局するところもあるけど、設備の老朽化や人手不足で閉局するケースもあるんだとか。
2024年の能登半島地震の時には、臨時災害放送局が設立されなかったことも、こうした課題を反映しているのかもしれません。
法政大学の北郷裕美教授は、「すぐに収益を上げる特効薬はない。でも、地域の人たちが参加できる番組を増やすなど、交流を深めて応援してもらえる放送局になることが大切」と話しています。
SNSやネット配信が当たり前になった今でも、災害時に頼れるのはやっぱりラジオなんだなと改めて感じました。
いざという時に情報が得られるように、普段からどんな放送局があるのかチェックしておくのも大事かもしれませんね!
GORI