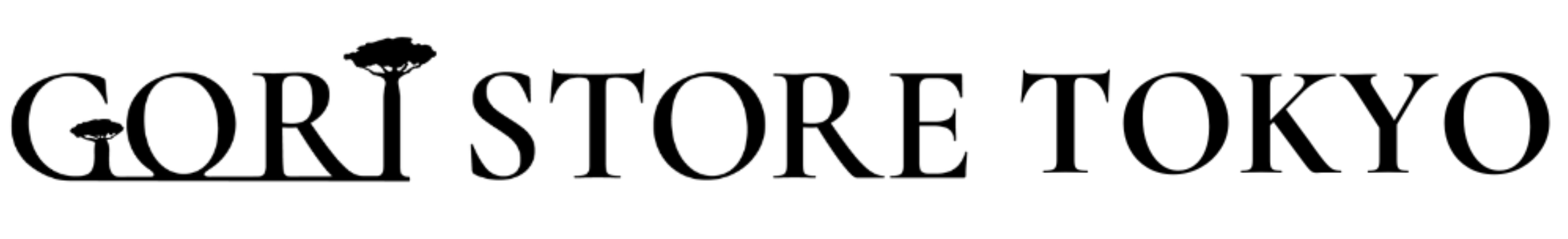こんにちは、GORIです。
最近、日本経済の大きなテーマになっているのが「最低賃金の引き上げ」です。政府は「2020年代に全国平均1500円」という高い目標を掲げています。もちろん、これは働く人にとっても重要なこと。でも、中小企業の経営から見ると、少し複雑な問題でもあります。
石破首相は、最低賃金の引き上げを実現するために「政策を総動員する」と表明。特に、最低賃金を目安より高く設定する都道府県には補助金や交付金を検討するとのこと。さらに、今後5年間は官公需を含めた価格転嫁の徹底や生産性向上支援にも力を入れる方針です。
しかしここで一つ疑問も。
本当に「補助金」を投入してまで賃上げ支援をするべきか?
例えば、2024年度は27県が中央の目安額を超えて最低賃金を引き上げました。徳島県では1人あたり5万円の一時金を中小企業に支給しています。確かに激変を和らげる効果はありますが、長期的に見ると企業の収益力強化には直結しません。
むしろ、補助金が常態化すれば「努力しなくても補助金があるから…」と生産性向上への意欲が薄れるリスクもあります。経営が厳しい企業が人材を抱え続ける状況は、地域全体の活力低下にもつながりかねません。
本来であれば、各地域が守るべき産業を見極め、その中で生き残る中小企業が「自力で成長」していける支援が大切。商工会議所などと連携して、新分野への挑戦や生産性の向上を促す取り組みが重要です。そして、従業員の「学び直し」や成長分野への労働移動も積極的に進めるべき時期に来ています。
もちろん、労務費が上昇する以上は「価格転嫁」も避けられません。発注側も下請け任せではなく、サプライチェーン全体の維持を考えた価格設定が必要です。こういう時こそ、公正取引委員会のような第三者の監視も大切ですね。
今日のGORI日記は少し硬めの経済のお話でしたが、花屋経営をしている私たちにとっても、経営のヒントになる話だと思います。
「外からの補助金頼みではなく、自社の体力をつける」ーー。
この視点をいつも持っていたいですね。
GORI