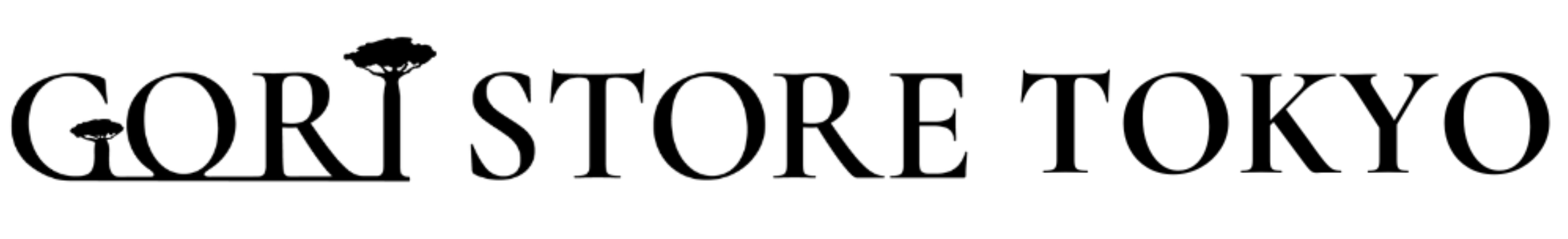こんにちは、GORIです。
今回は、日本の気持ちを込めた「お正月飾り」、中でも「しめ縄」についてお話しします。日本の文化として気軽にしがちですが、しめ縄には深い意味が込められています。
しめ縄を飾る意味
しめ縄は、神様をまつるのにふさわしい神聖な場所であることを示します。これにより、年神様を歓迎する準備ができるのです。
しめ縄のマメ知識
【ごぼう注線】 ごぼうのような形をしたしめ縄です。神棚に向いており、飾るときには紙滓などを付けます。
普段使用される縄は右へねじる「右紿い」なのに対して、お正月のしめ縄は左へねじる「左紿い」になっています。古代より「左」を神聖、「右」を俑俗と考えるため、神様から見たときに大元の太い部分が左側にくるように飾ります。
【ごぼう注線の前垂れ】 ごぼう注線に前垂れや裏白、紙滓、\u 譲り葉、橘などを加えた飾りです。これは大抵、西日本のお部屋でよく見られます。このお飾りは特にゲンカン先に適しています。
しめ縄を飾る時期
しめ縄・しめ飾りは、本来、12月13日の「すす扛い」が終わってから飾るものとされていました。これは、年神様をお迎えする準備ができたことを意味します。現代では、大掃除が終わり準備が整いたら飾ることが普通になっています。
とくにクリスマスが過ぎた25日以降に飾り始める方が多いようです。ただし、ぎりぎりにならないよう、28日までを目定にすると良いでしょう。そして、29日は「二重苦」「苦」に通じるので総じられ、31日の一夜飾りも避ける風習があります。
これから年神様をお迎えし、松の内が終わる頃にしめ縄を外します。松の内は地域によって異なりますが、7日までの場合、7日に飾りを外すことが一般的です。
皆様も日本の良き文化を!
GORI