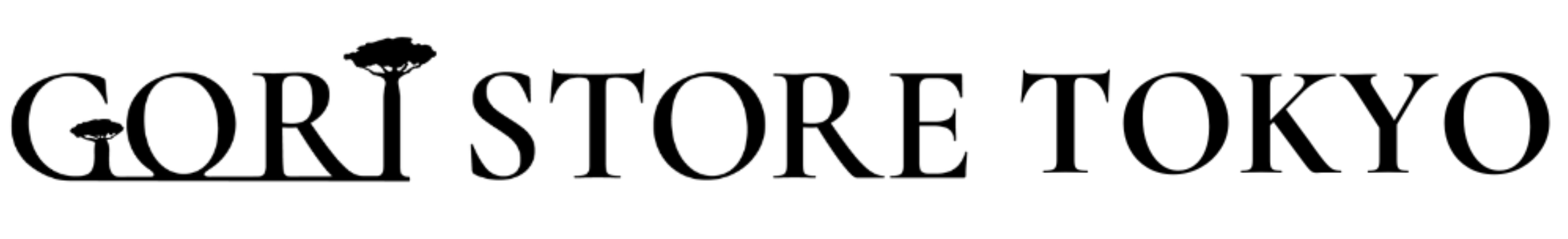こんにちは、GORIです!
クリスマスムードだった街並みも、今夜から一気にお正月モードに変わりますね。
地域によっては、すでに門松が飾られたお宅やお店も見かけるようになりました。
今回は、新年を迎える際に欠かせない「門松」について、その由来や役割、そして未来に向けて私たちができることを考えてみたいと思います。
門松の由来年神様を迎えるための目印
門松は、新年に訪れる年神様(としがみさま)を家に迎えるための大切な目印とされています。
年神様は、五穀豊穣や家族の健康、繁栄をもたらす神様で、日本では古くから松が神聖な植物として信仰されてきました。
特に松は、常緑樹であることから「永遠」や「不老長寿」の象徴とされ、神様が宿るのにふさわしい場所と考えられてきたのです。
門松に込められた3つの意味
-
松
松には、厄災や邪気を防ぐ力があるとされ、玄関や門に飾ることで家を守り清める役割を果たします。 -
竹
まっすぐに成長する竹は、「成長」や「繁栄」の象徴。未来への希望を感じさせてくれます。 -
梅
寒い冬でも美しい花を咲かせる梅は、「忍耐」や「生命力」の象徴。
この「松・竹・梅」の組み合わせが縁起物として重んじられ、門松に取り入れられています。
平安時代から続く伝統
門松の起源は、平安時代に遡るとされています。当時、門に松を立てて神様を迎える習慣がありました。
その後、武家社会を経て庶民にも広がり、江戸時代には現在のような形が確立されました。
現代の門松の意義
現代でも門松は、新年を彩る縁起物として親しまれています。
設置する際の注意点としては、以下の期間や日付を意識すると良いでしょう。
- 設置期間:12月28日~1月7日頃まで
- 避ける日:12月29日(「苦」を連想)、12月31日(一夜飾りは縁起が悪いとされる)
これらのルールも、昔からの習慣として受け継がれている大切な文化です。
門松の未来、伝統を次世代へ
残念ながら、近年では門松を飾る家庭やお店が減少し、また生産者さんも年々少なくなっています。
一部では、本物の竹や松ではなく、造花の門松が主流になるのではないかという声も聞かれます。
しかし、この素晴らしい日本の文化を次世代に伝えていくためには、私たち一人ひとりが門松の意味を理解し、積極的に取り入れていくことが大切です。お正月の準備を通じて、家族や友人と日本の伝統について話し合う時間を作るのも素敵ですね。
GORI